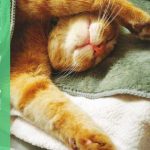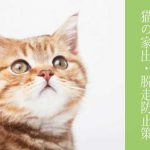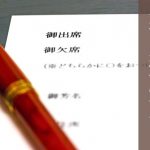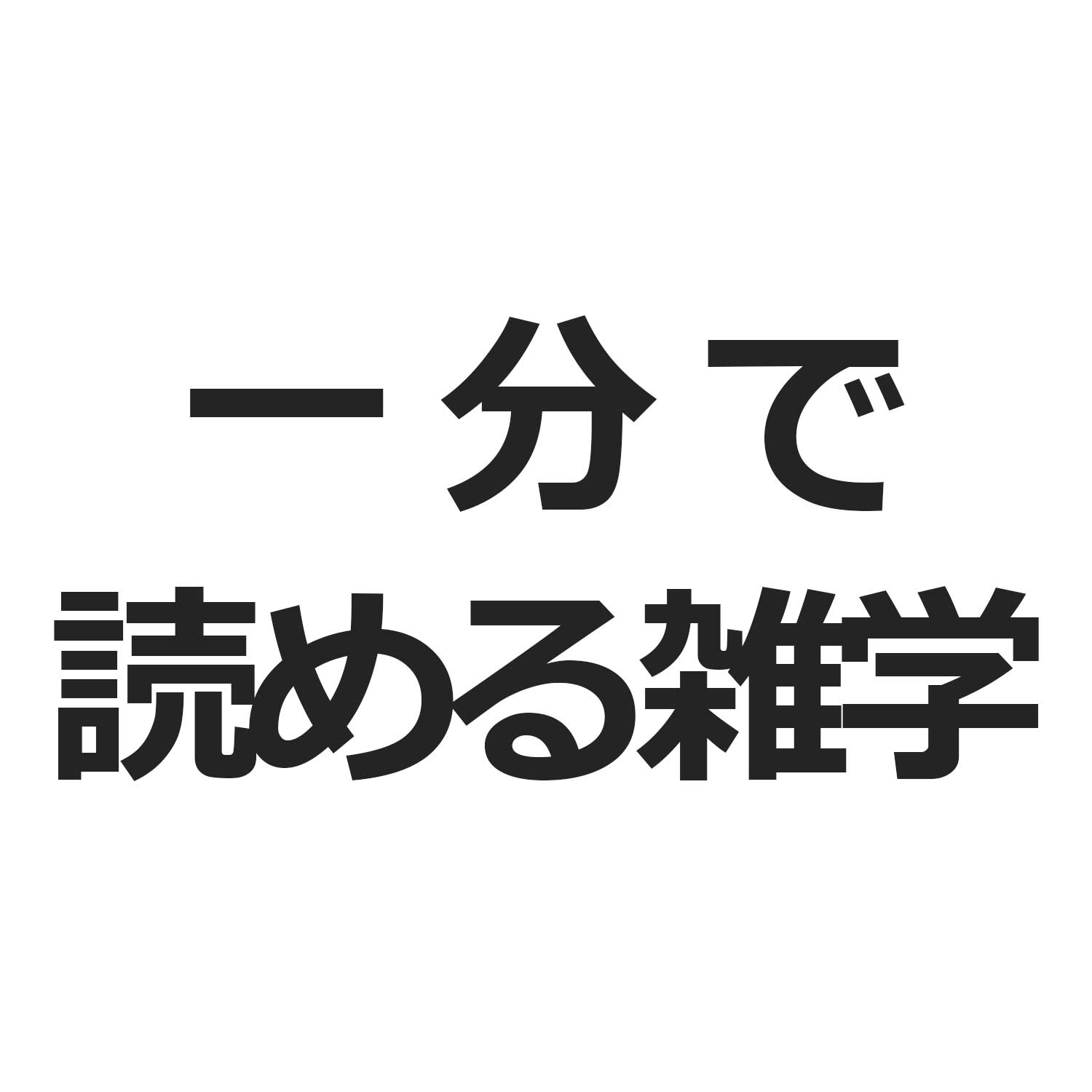2024/10/11

我が家の猫が家出、失踪してしまったら、居ても立っても居られないという気持ちは非常によくわかります。
しかし、いざいなくなった場合、何から始めたらよいかわからないかもしれません。
この記事を見て、できることから初めてください。
Contents
猫が迷子になったらやるべきこと
最も重要なのはチラシやポスターを作ることです。
ポスター、チラシを作って貼る、配る
ポスターとチラシが最も重要です。
ポイントを並べておきます。
- カラーで作る
- サイズはA4かB5
- タイトルは『猫を探しています』と、大きく書く
- 写真は必須
- 特徴は写真ではわからない部分を書く(写真で見えない部分や鳴き方の特徴など)
- 目撃情報を求める(ささいなことでいいのでご連絡くださいと書く)
- 飼い主の心情を短く(必死で探していますなど情に訴える内容を一言で)
コチラのサイトに良いテンプレートがありましたのでご活用ください。
作ったポスターは近くの動物病院やコンビニ、飲食店などに貼らせてもらいましょう。
電柱などは電力会社所有のものなので、勝手に貼ると軽犯罪法違反に触れることがありますので、気をつけましょう。
また、チラシは一般家庭にポスティングするとよいでしょう。
公的機関に届ける
警察・動物愛護センター・保健所・犬猫病院などに届け出てください。
迷子札を見て、連絡してくれることがあります。
こちらのウェブサイトに詳しく書いています。
ネットに書き込む
ツイッター、フェイスブック、SNS、猫探し掲示板 etc…。
ありとあらゆるツールを使いましょう。
猫探し掲示板はコチラなどをご覧ください。
ペット探偵に頼む
自分ではとても探せそうにないときはペット探偵に頼むのも一つの手です。
料金は安くありませんが、プロに任せることも考えてみてください。
スポンサーリンク
猫を探すときに持って行くもの
最低、これだけは持って行きたいというものです。
- スマホ(携帯電話)(連絡用、猫の画像用)
- チラシ
- ポスター(とそれを貼る道具)
- キャリーバッグ(トイレシートを敷いておく)
- 猫が普段食べているご飯(もしくはおやつ)
- 懐中電灯(夜間捜索時)
スマホは連絡用になりますし、また捜索を手伝ってくれる人や誰かに聞くときに猫の画像を見せることができますので便利です。
チラシには載せられる画像が限られますので、スマホに写真を入れておきましょう。
正面画像からはわかりにくいシッポの特徴や毛色の特徴も容易に見て取れます。
それから、猫が普段食べているご飯も持って行きましょう。
缶詰を食べている場合はプルタブを『カチッカチッ』とする音に反応するかもしれません。
またカリカリを食べている場合、それをビニール袋に入れて持って行き、見つけたときにそれで呼び寄せることができます。
その他の必需品、アニマルキャッチャー
少し大掛かりになりますが、成功の確率が高いので是非設置しましょう。
大きさにもよりますが、5,000~12,000円くらいのものが多いようです。
また、動物保護団体、ボランティア団体、動物病院のようなところで貸してくれることもあるようです。
(有料・無料両方あります)
アニマルキャッチャー設置方法
逃げた場所に置いてください。
私有地の場合、トラブルを防ぐため所有者に許可をとって設置してください。
踏板式と餌吊式があります。
中へ誘導するため、両方とも手前に少量のエサを置いてください。
- 踏板式の場合・・・猫缶などニオイの強い食べ物を奥に置いてください。
- 餌吊式の場合・・・猫が好みそうな食べ物を吊ってください。(魚肉ソーセージやチクワなど好みに合わせて)
それから、入り口付近に家から持ってきたトイレ砂を置いてください。(容器に入れて)
また猫が愛用しているタオルや毛布など自分のニオイがするものでアニマルキャッチャー全体を巻いておくと警戒感が薄れます。
日ごろ使っている座布団などを置いておくのもいいと思います。
猫の習性から探し方を考える
猫は縄張り意識の強い生き物です。
安心できる安全な場所から離れることを嫌がります。
ということは、まずは最初に逃げ込んだ場所、もしくはその近くにいると考えるのが定石です。
まずは、最初に逃げ出した事件発生現場の近くから探してください。
特に、狭くて猫が潜り込める場所を中心に捜索してください。
駐車場の車の下などに隠れていることがよくあります。
人間とは違って、猫は意外なほど長時間、ジッと隠れています。
不安と恐怖で動けなくなっているわけです。
数日間も同じ場所にいたということも珍しくありません。
すぐ近くにいなくても行動範囲を考えて捜す
また、すぐ近くにいなかったからといって焦る必要はありません。
徐々に捜索範囲を広げてください。
猫の行動範囲はさほど広くありません。
去勢オスで半径200~500m
去勢していないオスで半径500m~1km
を目安にしてください。
(メスはもう少し範囲が狭いようです)
そして、一日の行動距離は去勢オスで25~50mです。
まずはこれらの数字を目安として、捜索の範囲を決めてください。
猫を探す時間は午後から夕方にかけて
いなくなったとわかったら、すぐに探し始め、その日のうちに見つけたいですが、そういかなかった場合は探す時間帯を考えましょう。
猫は元々、夜行性の生き物です。
若い猫が夜中の大運動会を繰り広げるのは、この習性が色濃く残っているからです。
しかし、人間と暮らしていると徐々に人間の生活時間帯に合わせるようになります。
人間が寝ている夜は、猫も寝ていることが多くなります。
つまり、猫を探すのは夜を避けて、お腹を減らして行動している時間がよいということです。
ですので午後から夕方が最適だということになります。
また、単純に夜は見えにくいということもあります。
人間も猫を見えにくいですが、猫は人間以上に目が悪いので恐怖を感じて逃げてしまうことになりかねません。
見つけたときは慎重に
猫を発見したとき、慌てて追いかける(近づく)のはやめましょう。
気持ちはわかりますが、猫は目が悪いので飼い主だと気づいていない可能性があります。
ゆっくりと歩き、声をかけてあげてください。
そして、猫が警戒心を解く様子を見せたら近づき、そっと抱きかかえ、キャリーバッグに入れてください。
ここで焦ってそのまま抱きかかえて帰ろうとすると、また逃げてしまうということにもなりかねませんので、捜索時にキャリーバッグは必携です。
スポンサーリンク
猫が迷子になる理由
猫は縄張りを作って暮らす動物です。
その縄張りとは、猫にとって『安心していられる場所』です。
これは裏を返せば、縄張り以外の場所は不安になるという意味です。
たとえば動物病院に行くとき、キャリーバッグに入れた瞬間、猫がなきわめくのは縄張りの外に連れ出されることがわかっているからです。
ここからが重要なのですが、なんらかの拍子でキャリーバッグのドアが開き、猫が外に出てしまったとします。
すると、猫は不安が最高潮に高まってしまい、とにかくどこでもいいから身を隠せる場所に逃げ込もうとします。
これは飼い主が傍にいてもいなくても変わりません。
それが猫の習性なのです。
あっという間に飼い主の見えないところまで走って逃げてしまいます。
これこそが、猫が迷子になる一番の理由です。
猫は自分の家から逃げ出さない!?
最後に、猫の習性をもう1つ紹介しておきます。
それは、
(室内飼いの)猫は決して家から逃げない
ということです。
「いやいや、うちの猫は逃げ出して大変だった」とおっしゃる方もいるとは思います。
しかし、それは『逃げた』というより、好奇心から外に出て帰れなくなったという方が正しいと思います。
というのも、(室内飼いの)猫にとっては、家こそが自分の縄張りです。
最も安心していられる場所なのです。
そこを逃げ出す理由がありません。
『逃げた』と感じてしまうのは、室内飼いが猫を閉じ込めているという意識があるからだと思います。
猫自身は恐らくそういう風に思っていません。
そして、『逃げた』と思ってしまうと、遠くを探してしまうことになりがちです。
まずは、出て行ったと思われるところのすぐ近くを探してください。
特に、狭くて潜りこめそうな場所を覗くと、見つかる可能性が高くなります。
猫が外を見ているのは見張りをしているだけ
室内飼いの猫にとって窓やドアというものは、縄張りの境界線です。
その内側と外側で猫の心理は大きく違います。
とはいえ、窓やドアが開いていれば、「ちょっと出てみようか」と思うのが人情(猫情?)です。
若い猫ほど好奇心が強いので、そう思ってしまうようです。
そして、ついつい出てしまうのですが、そこで不安になり、パニックを起こし、どうしたらいいかわからなくなるというわけです。
繰り返しますが、猫は基本的に自分の縄張りを離れたがりません。
特に、家の中は慣れ親しんだ縄張りですし、優しい飼い主がいます。
そこから離れたがる理由が見当たらないのです。
窓から外をじっと眺めて出たそうにしている様子を見ると、「出たいのかな?」と思います。
しかし、それは
自由になりたい
と思っているのではなく、
なわばりの外を見張っているだけ
です。
そういった猫の心理を正しく知り、いざというときに的確な対処ができるように、日ごろから備えておきましょう。
【関連記事】